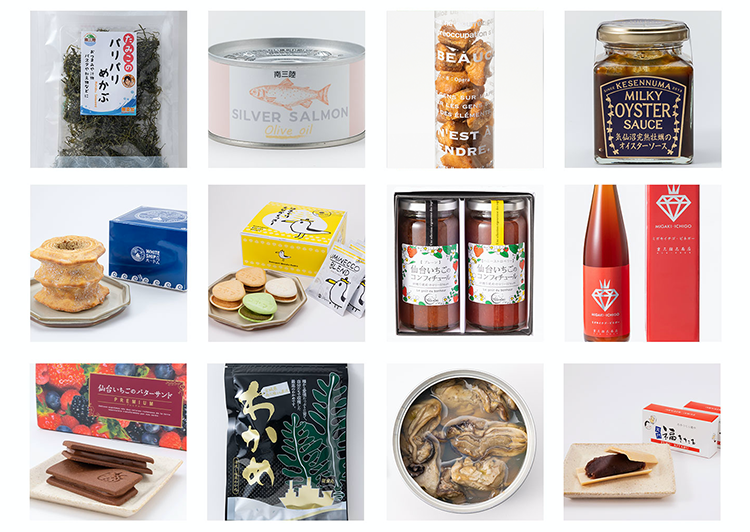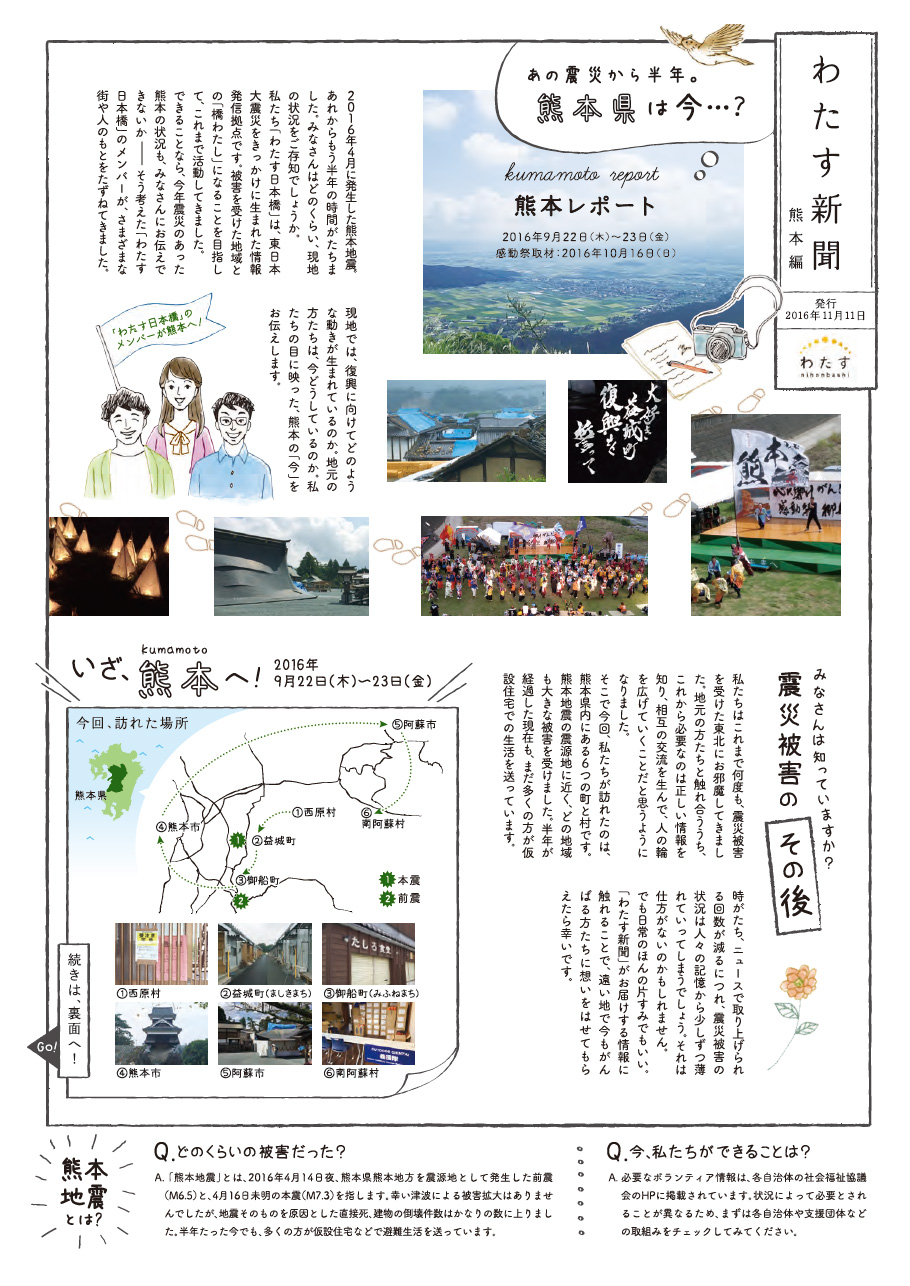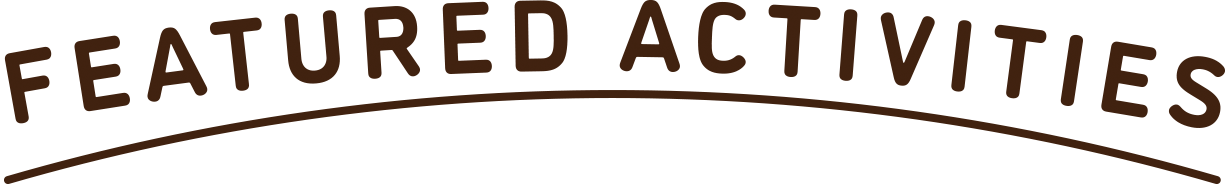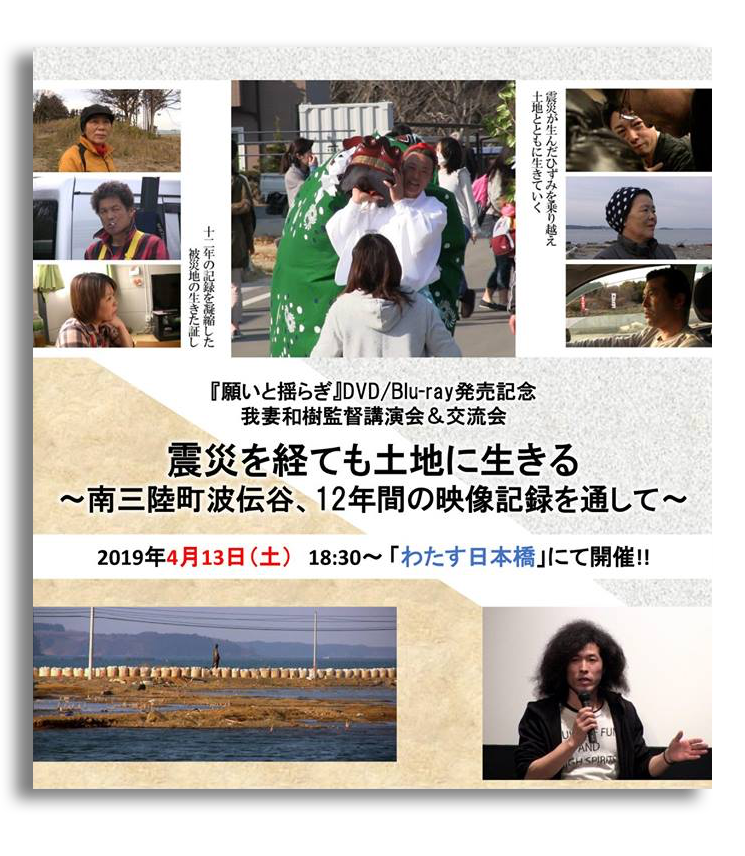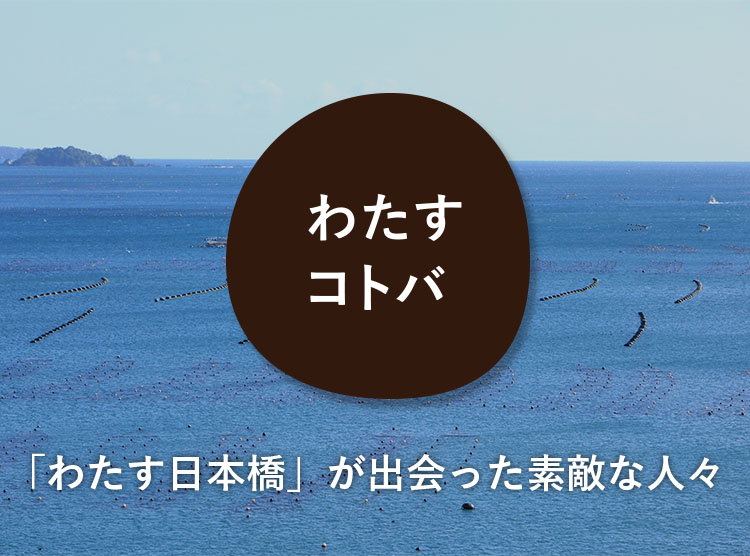わたすマーケット&ギャラリー
コンセプトは土間。ふらっとお立ち寄り
いただける
「わたす日本橋」の
オープンスペースです
「知る、見る、使う」。
マーケットでちょっと買い物したり、ギャラリーの展示で何かを感じたり発見したり。
「橋わたし」したい、人・モノ・コトを発信。
わたすギャラリー展示
わたすギャラリーでは、東北のさまざまな情報を発信しています。
ご来店の際には、是非ご覧ください。
わたすマーケット&ギャラリーはフリースペースです。どなたでもご自由にご覧いただけます。

2025.03〜
「わたす日本橋10年企画」

2024.09~2025.03
「東北のおやつ」
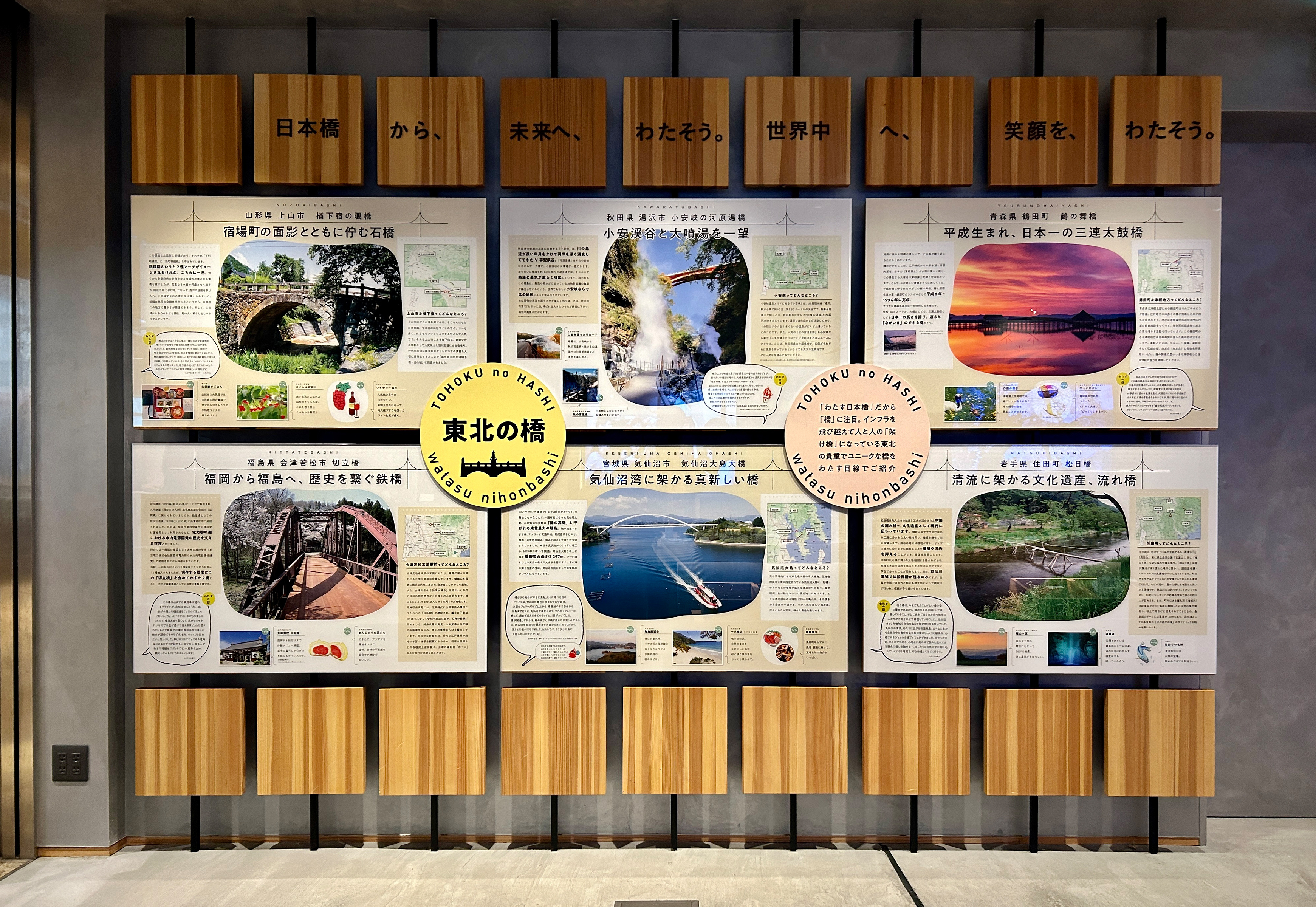
2024.03~2024.09
「東北の橋」
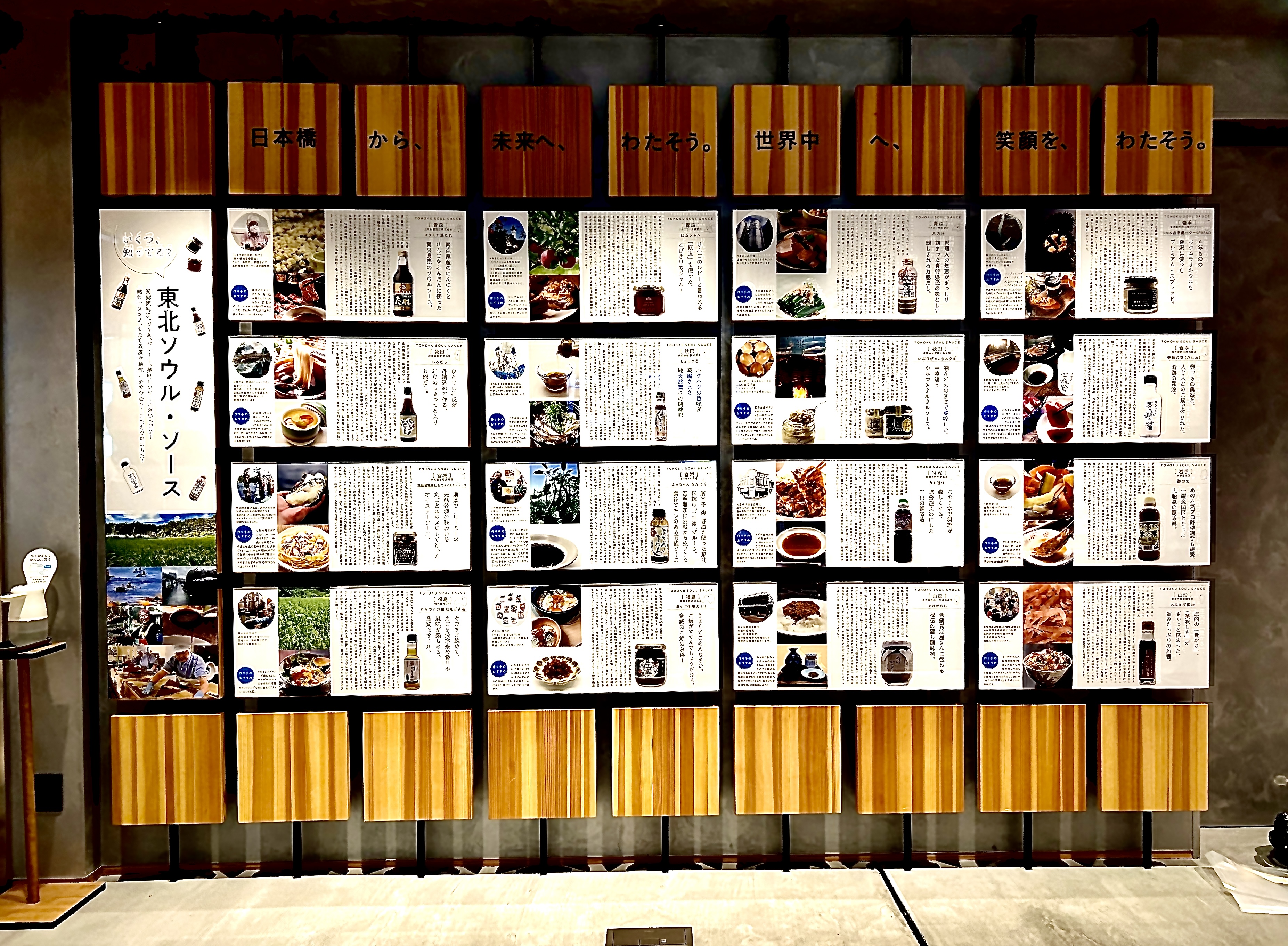
2023.09~2024.03
「いくつ知ってる?東北ソウル・ソース」

2023.03~2023.09
「東北の田園に行こう」

2022.09~2023.02
「東北のおいしいもの」
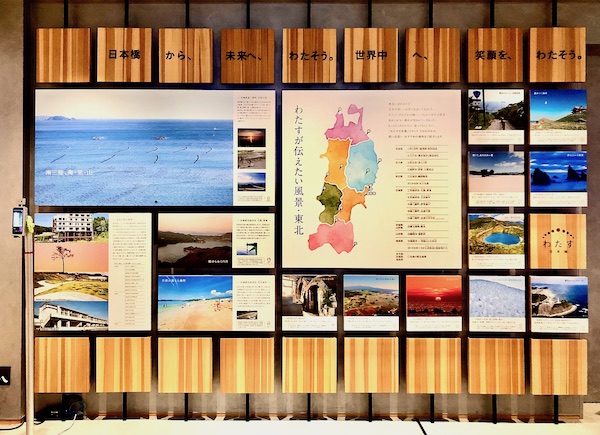
2022.03~2022.08
「わたすが伝えたい風景・東北」

2022.02~2022.03
「南三陸中学校写真コンクール」

2021.03~2022.02
「わたすコトバ・わたすキロク」
わたすが選んだ「おいしい東北」市

2021.03.03〜
「わたす日本橋」スタッフが、東北に通う中で出会った「おいしい味」を日本橋で販売します。
地元で人気のスイーツや、特産フルーツを使用した食品、ミネラルたっぷりの乾物、魚介調味料など、ぜひお楽しみください。