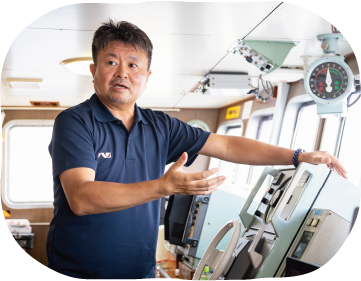狩猟は、牡鹿半島の森を見つめること
Antler Crafts(アントラークラフツ)の小野寺望(のぞむ)さんは、牡鹿半島で20年以上ハンターを続けてきました。狩猟した鹿や鴨を自ら加工してジビエとして提供しています。
狩猟は、豊かな生態系を育んできた牡鹿半島の森を生き物の目線で見つめることでもあり、いのち一つ一つへの感謝やリスペクトを感じることでもあるという望さん。しかし、近年は、環境の変化もあり鹿が激増して、それ以上の狩猟を余儀なくされ、崇拝していたものや大切にしていた想いが踏みにじられていくような気持ちになったといいます。だからこそ、一頭一頭の命を無駄にせず「食」から環境と向き合う取り組みやワークショップ等の活動を始めました。